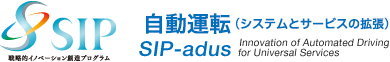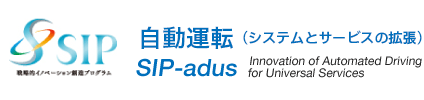市民ダイアログ2018
戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)自動走行システムでは、自動運転に対する社会受容性の醸成を目的とした取組みとして、「戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)自動走行システムシンポジウム」を開催しました。
・第1回 市民ダイアログ(シンポジウム) 平成30年10月7日(日) 「あなたと考える自動運転の安心・安全」
・第2回 市民ダイアログ 平成30年12月4日(火) 「地域で創るモビリティサービス」
第1回 市民ダイアログ
◆ テーマ
~あなたと考える自動運転の安心・安全~
1.開催趣旨
戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)自動走行システムでは、更なる自動走行システムの社会受容性の醸成に向け、自動運転に関する市民の理解向上と社会的受容性の醸成を目的にシンポジウムを開催しました。
産学官を代表する専門家による正確な情報提供の場を設けることで、市民の自動運転に対する不安を取り除き、正しい理解を深めることを目的として実施しました。
2.観覧方法
◆ 事前登録制(定員に空きがある場合は、当日先着順で受付予定)
当日来場者数 194名
3.開催概要
◆ 日時 平成30年10月7日(日) 10:00~12:00(開場9:30)
◆ 場所 東京国際交流館(東京都江東区青海2-2-1 国際研究交流大学村)
ゆりかもめ「船の科学館」東口より 徒歩約3分
りんかい線「東京テレポート」駅B出口より 徒歩約15分
◆ モデレーター
SIP自動走行システム推進委員会構成員 国際自動車ジャーナリスト 清水和夫氏
◆ 司会
SIP自動走行システム推進委員会構成員 モータージャーナリスト 岩貞るみこ氏
◆ 登壇者
SIP自動走行システム・プログラムディレクター 葛巻清吾氏
SIP自動走行システム・サブ・プログラムディレクター 有本建男氏
国土交通省 自動車局 技術政策課 自動運転戦略室長 平澤崇裕氏
警察庁 交通局交通企画課自動運転企画室長 杉俊弘氏
日本自動車工業会 自動運転検討会主査 横山利夫氏
中京大学 専門教授 中川由賀氏
東京農工大学 准教授 ポンサトーン・ラクシンチャラーンサク氏
4.開催内容
本シンポジウムでは、「あなたと考える自動運転の安心・安全」をテーマに、国土交通省や警察庁、日本自動車工業会、大学・研究機関の各方面で安心・安全について取り組む専門家がパネルディスカッションを行い、「自動運転はどれだけ安全でなければならないか」、「自動運転の事故の責任問題」、「自動運転の国際連携」などに関して議論をしました。
自動運転の技術や関連の法規制等に関し、国の活動状況や今後の課題について、様々な観点から意見交換を行いました。
5.関連資料
第1期&第2期 SIP-adusの取組み
(SIP自動走行システム・プログラムディレクター 葛巻清吾氏)
自動運転の実現に向けた取り組みについて
(国土交通省 自動車局 技術政策課 自動運転戦略室長 平澤崇裕氏)
自動運転の実現に向けた警察の取組について
(警察庁 交通局交通企画課自動運転企画室長 杉俊弘氏)
あなたと考える自動運転の安心・安全 自工会の取り組み
(日本自動車工業会 自動運転検討会主査 横山利夫氏)
ヒヤリハットデータベースを活用した予防安全の進化
(東京農工大学 准教授 ポンサトーン・ラクシンチャラーンサク氏)
自動運転をめぐる法的責任
(中京大学 専門教授・弁護士 中川由賀氏)
(SIP自動走行システム・サブ・プログラムディレクター 有本建男氏)
6.シンポジウムの様子


第2回 市民ダイアログ
イベント概要
今回は、市民ダイアログ初となる地方開催地となる、香川県小豆郡(小豆島)で開催しました。
小豆島の住民の皆様や交通事業者、SIP関係者等、計20名が参加し、移動に関する課題やニーズ、自動運転への期待・不安などについて、対話形式で意見を出し合い、小豆島の理想の未来像を描いていきました。
◆ テーマ
日本の未来図 小豆島 ~地域で創るモビリティサービス~
◆ 開催日時
- 2018年12月4日(火) 12:00~15:00
◆ 開催会場
- 香川県立小豆島中央高等学校 大会議室(香川県小豆郡小豆島町蒲生甲1001)
◆ 参加者
-
SIP自動走行システム:プログラムディレクター 葛巻清吾氏
SIP自動走行システム:サブ・プログラムディレクター 有本建男氏
SIP自動走行システム:推進委員会構成員 国際自動車ジャーナリスト 清水和夫氏
SIP自動走行システム:推進委員会構成員 モータージャーナリスト:岩貞るみこ氏
市民パネリスト 16名
◆ 関連資料
◆ 開催レポート
- 今回の市民ダイアログは、市民ダイアログ初の試みとなる地方開催となり、地域に根差した課題、ニーズ・期待や、将来のモビリティサービス像について語り合いました。
自動運転は、元気な高齢者が活躍できるようになるといった、人の可能性を広げていくことに対する期待があると共に、「機械だけでは成り立たず、人が常に中心で助け合う必要がある」、「AIが入ってきても人が共感できるシステムであるべき」といった、技術開発が進んでも、人を中心とした自動運転を期待する声や、「多様なデータを共有し、連携することで、小豆島の人が望むサービスを提供できるようになる」、「データを活用し、小豆島の独自の物差しで小豆島の元気を測り、モビリティサービスを考えていきたい」といった、データを活用することで小豆島の住民が望むサービスが実現していけるのではないかといった未来志向の意見が出されました。
その他、テーマ毎に以下のような意見があがりました。
テーマ1:移動・交通に関する課題・ニーズの共有
「90歳を過ぎても自家用車を運転する人が少なくない。高齢者同士の乗り合わせも多く、家族も心配している」
「夜間には孤島になることが課題。急患の場合、夜はヘリが飛べず、高松から救急艇を待つ必要がある」
「公共交通のダイヤによって外出を断念することがある。小豆島特有のイベントもあるので、色々な地域と交流できる島になってほしい」
「普段は車のほうが便利なため、公共交通は使わない。ドライバー不足や採算性等、問題があることは理解しているが、利便性が向上されないと利用者も増えない」
テーマ2:これからの移動・交通のあり方、自動運転の活用
「仕事を持たない元気なおばあちゃんが観光客や若い人とおしゃべりをしながら島内を走り島内案内をするサービスが可能になるのでは」
「主要地域はバスがあるが、自宅からバス停までの交通が無く、そこに自動運転車があれば便利だと思う」
といった自動運転への期待と共に、
「田舎道を走るバスは低速で、一般車両をうまく追い越させるようにしているが、AIや自動運転にそういったことができるのか」
「高齢者は乗降支援が必要な事が多く、無人走行車の場合は怪我のリスクが懸念される」
といった自動運転への不安に関する意見もきかれました。
最後に、SIP自動走行システム推進委員会構成員より、「移動は手段であり、移動した先になにがあるのか考えていく必要がある。モビリティが多様化すればコミュニティも多様化する」、またSIP-adusの有本サブ・プログラムディレクターよりは、「地域で初めて開催した今回の市民ダイアログ自体が実験。今回の議論を持ち帰り周囲の人たちと話してほしい」といった総括をうけ、市民ダイアログは閉会しました。 -
【第2回市民ダイアログ 実施風景】






-
【グラフィックレコーディング】